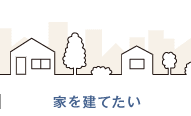○屋根材の種類
屋根材には大きく分けて粘土系、金属系、スレート系と3種類ありあります。
○屋根材それぞれの特徴
粘土系は、粘度を成形して焼いた屋根材で、形によって和瓦と洋瓦に分けられます。また、いぶし瓦、陶器瓦、塩焼き瓦などの製法があります。
瓦葺きは耐火、防水、断熱、遮音性に優れていますが、重量があり地震などには弱いといわれてきましたが、現在の木造を中心とする構造が飛躍的に丈夫になってきていることと前述の性能に意匠の豪華さが相まって選択する住宅購入予定者も微増しています。
価格的にも、総2階の30坪程度の一般的住宅ですと屋根の平米数も少ない為、他材と比較しても建築総金額からすると大きな差額にはなりません。
洋風住宅には洋瓦のヨーロピアンやスパニッシュタイプなどが人気です。
金属系は、鋼板、銅板、アルミニウム板、ステンレス板などの種類があります。
金属板は、加工しやすく、施工性がよいのですが、さびやすいという欠点があります。また、銅板やステンレス板はかなり高価です。一般の住宅には、表面に塩ビ塗料などを焼き付けてさびを防いだカラー鉄板がよく使われていて、シンプルな仕上がりとなりコスト的にも安価といえます。
スレート系は、セメントと繊維を原料としてつくられており、薄い板状の屋根材が主体で軽量な上、施工も容易コストも比較的安価で色数も豊富なので、現在最も多く使われている屋根材といえます。
平板状のほかに、洋瓦の形をしたものが普及してきており、意匠的には粘土系のものと変わらずコスト的に安価な為選択する住宅購入予定が増えています。
※屋根工事は、材料コストのみでなく屋根形状やデザインによって金額が大きく変わります
モリス住宅総合研究所 監修
カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »
2010年7月17日
○内装仕上材
床、壁、天井の仕上材が主なものとなります。
○床の仕上材
下地の根太(木材)に合板下地を貼り、その上に仕上げ用の床材を貼る施工方法が一般的です。
もっとも普及している仕上材は、フロアーと呼ばれる厚さが12ミリないし15ミリの合板に化粧単板(0.3ミリ~0.5ミリ)を貼ったもので、一枚のサイズが1818ミリ×303ミリのものが主流ですが、化粧単板が2ミリ、3ミリある、高級で表面単板の傷みにくいものや、床暖房(電気式)を組み込んだものがあります。
通常の化粧単板仕様のものは、掃き出し等の水にさらされる可能性の有る箇所では単板がはがれたりすることもあるのでサッシの開閉等注意する必要があります。
又、キャスターつきの椅子等の使用に不向き(へこんだり、表面単板がはがれる恐れがある)なフロアーや、薄い化粧単板仕様のフロアーの中にも下地を硬いものにし、樹脂を含浸させた単板を貼った強化フロアーもありますので事前に確認することが大切です。
又、断面形状や長さは上記と同じでも、小幅の高級感があるものもあります。
表面の化粧単板の樹種としては、ナラ、ブナ、サクラ他様々あり、さらに幾種類かの着色を施すことによって、ナチュラル色からダーク色まで様々な選択ができます。
前述しました合板下地をベースとするものに対して、無垢仕様のものがあります。
一般的なサイズとしては厚さ15ミリないし18ミリで、一枚のサイズが1818ミリ×巾75ミリ程度のものが主流で、樹種としては、ナラ、ブナ、サクラ他様々ありますが、最近では東南アジアのチークや中南米のイペやアフリカのエッキやオーストラリアのサイプレスなどの非常に硬く、意匠(デザイン)的にもマニァックなものも各種出廻っております。コスト的には大きくアップしますが数十年使用すると考えれば検討の余地もあるでしょう。
床材の仕様や色を決めるに当たっては、コンセプトを考えたうえで、外観、間取りから他の内装仕上箇所(壁、天井)や建具や照明まで考慮して選択してゆくことが大事ですので、建築会社の担当者に“つくりたい住宅”のイメージを充分理解してもらったたうえで、総括的なコーディネートをしてもらうことをお勧めします。
自分たちのコンセプトを絞り込むに当たっては、様々な建物を見て廻ることが重要ですが、住宅展示場等の、建坪が広く又、実生活が感じ難い物件よりも、現場見学会等が参考になるかと思います。
モリス住宅総合研究所 監修
カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »
2010年7月17日
主な内装下地材
天井や壁のクロス下地や床下地には様々な合板や石膏ボートが使用されていますが、使用する場所や条件によって
最適なものを選ぶことが重要です。
合板
特徴としては、伸び縮みが少なく、厚さに比例して(プライ数:貼合わせの枚数)強度性能が高く、加工し易い建材です。
○合板(普通合板)
普通合板 :従来からベニヤ板と言われていた合板で、一般的に広く使われる。
コンクリート型枠用合板 :コンクリート打込み時にその型枠として使用される合板。
構造用合板 :建築物の耐力構造上必要な下地(屋根、外壁、床)に使用される合板。
難燃合板・防炎合板 :燃え難くした合板で、建築基準法による内装制限箇所に使用する
○特殊合板
天然木化粧合板 :突き板合板と呼ばれ、合板下地に様々な無垢材の薄い短板を貼った物。
特殊加工化粧合板 :化粧プリント合板が主流で押入内部や建具に使われる。
内装や下地に使用する合板は、シックハウス症(化学物質過敏症)を抑える為の建築基準法の改正により、合板に含まれるホルムアルデヒド等の化学物質を極力抑えた合板の使用が義務付けられ、★マークでその等級が表示されていますので、建築やさんに詳しく仕様を確認することも大事です。
石膏ボード(ブラスターボード)
特徴としては、化学物質をほとんど含まず、燃えにくく、吸音、遮音性能が高い建材です。
ブラスターボード :厚さは、9.5ミリ、12.5ミリ、15ミリ等がありますが、使用の主流は12.5ミリになってきています。
耐水ブラスターボード :耐水性に優れた石膏ボードで洗面所等の水廻り部分の壁、天井の下地
に使用します。厚さは、9.5ミリ、12.5ミリ
化粧ブラスターボード :表面を化粧加工した石膏ボードで仕上材として使用します。
ラスボード :真壁和室の塗り壁の下地に使用する厚さ7.5ミリの下地ボードです。
最近は、真壁和室でも下地をブラスターボードにし、仕上げを洒落た
和風クロス(和紙風、塗り壁風等)にするケースも多いです。
石膏ボードの中には、新築住宅などで発生するホルムアルデヒドを短時間で吸収分解する物や、鉛合板を貼って遮音、遮X線性能を高めたものや電磁波を防ぐ物等、様々な仕様があるので詳しく調べてみるのも面白いですね。
モリス住宅総合研究所 監修
カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »
2010年7月17日
外壁材の選び方
意匠性
外観(形状、屋根材、サッシの種類カラー)や敷地の条件を考慮することが大事で、複合材(例:鋼板サイディングと窯業系サイディング
の組み合わせ)の使用も可能ですが、 住宅会社のアドバイザーの意見や施工物件その他を見て検討することが必要です。
又、色調についてもあまり目立つものは避けた方が厭きもこなく賢明といえるでしょう。
対劣化性能
最近の材料、工法については比較的劣化の速度が遅いものが増えてきましたが、外壁の種類毎に以下の注意事項やメンテナンスの
必要性は知っておくべきです。
湿式工法(モルタル下地+リシンかき落し、リシン吹き付けタイル等)では、クラック(ひび割れ)が発生することがあります。
乾式工法の中で、窯業系サイディング(現在の住宅の大半に使われている)は、施工上ジョイント部分にコーキングを充填する為
10年以上経過した後にコーキングの打ち直しの必要が生じることを知っておいて下さい。
ALCやスレート系でもジョイント部にコーキングが充填されていれば同様です。
金属系サイディングでは、塩害の発生が懸念される地域では材料の選択や施工方法を検討することが大事です。
他、塗装の劣化(退色)によっては再塗装の必要も出てくることがあります。
窯業系サイディングについては、メーカー塗装品(現場塗装を避ける)を選ぶことがベストでしょう。
断熱性能
外壁材単体でみることよりも、様々な高性能断熱材を使用する住宅会社が多くなって来ていますので、断熱の仕様を比較、
確認することが大事です。
防火性能
ALC、窯業系サイディングの防火性能は確立されており、金属サイディングなどについても単体で防火性能が劣るのであれば、
下地材に防火材を施工し数値をクリアしますので心配は不要です。
火災時に延焼のポイントとなるのは開口部であり、その辺りの設置位置、仕様等の検討が大事です。
コスト
一般的な窯業系サイディングを選択することが無難といえます。
モリス住宅総合研究所 監修
カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »
2010年7月17日
外壁材の種類と特徴
外壁材を工法別に分けると湿式工法と乾式工法に分けられます。
湿式工法とは、現場でのコンクリート打ちや左官工事など、水を使う工法です。高級感がある仕上げのものが多いのですが、天候に左右されやすく、施工管理にたよるところが大きいので、工期に余裕を持たせなければなりません。
湿式工法にはモルタル(セメントと砂を水で練り混ぜて塗装した外壁)やリシンかき落し、リシン吹き付け(モルタル下地の上に細かい大理石を混ぜた色モルタルを塗り、乾き切らないうちにクシ状の金属でかき落とす工法や吹き付ける工法)や吹き付けタイル(モルタル下地の上に仕上げ材料を吹き付け、セラミックタイルに似た光沢のある模様をつくる工法で、場合によっては、表面をローラーやコテなどで抑えることもあります)等があります。
最近では、乾式下地材(窯業系サイディング素地)施工の上に湿式仕上材を施工したり、難燃性の硬質断熱下地材に同様の仕上げを施したりする複合的な工法も開発され、断熱、耐火に対してもより大きな性能を付加してきています。
乾式工法とは、パネルなど(工場生産品もしくは工場加工品)をボルトや釘、ネジ、アングル等で取り付ける工法で、現場の施工では水は全く使いません。湿式工法で必要な乾燥待ちの必要がないため、短期間で工事が終了しますが目地等のシーリング処理が重要な施工ポイントになります。
乾式工法には、木質系(美しい木目を活かした日本の伝統的な工法ですが、防火の面で問題があることから、法律によって使用できない区域もあります) やサイディング(工場で一定の形につくった板を現場で釘などを使って下地に止めていく方法で主な材質には、窯業系と金属系があり耐火性、耐水性に優れています)やALC壁(工場でセメント、珪石生石灰、水、発泡剤を混合して形成し、高圧高温で養生した軽量気泡コンクリートのパネルで耐火性に優れています)やスレート系(セメントと特殊鉱物質を原料としてつくられており、屋根材として使われることが多い中で外壁材に使われるケースも少なくありません)等があります。
最近の外壁の仕様の大半が乾式工法で施工されており、中でも窯業系サイディング(耐火性に強い石綿、珪酸類を原材料に作られており、表面のパターンや凹凸やカラーは多種に及ぶ)が主流となっています。
モリス住宅総合研究所 監修
カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »
2010年7月17日
3回に分けて外壁材についてのお話を致します。
外壁材とは、住宅の外周部を覆う壁部分に使用する材料や施工方法(複合材の組み合わせ、混ぜ合わせ)を言いますが、使用する素材、仕上り材、施工方法により様々な質感や表現を可能としその住宅(和風、洋風、モダン、シック等)にふさわしいものを選ぶ(組み合わせる)ことが大事です。
又、建築基準法で規定された防火材料の使用が義務付けられている地域が大半で、その区分に該当する材料や工法を選ぶことが重要です。
種類としては不燃材料、準不燃材料、難燃材料、準難燃材料があります。
○不燃材料
通常の火災に対し燃焼せず、有害な煙などを発生しないことが前提で、 コンクリート、レンガ、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、
ガラスモルタル、しっくい等
上記に類するもので、建設大臣が指定するものを言います。
細かくは、耐火時間や材料の厚さや含有物なので厳密に分類されますが概要としては以下のように分類できます。
○準不燃材料
通常の火災時にはほとんど燃焼せず煙も微量、有害ガスもほとんど発生しないことが前提で、木毛セメント板、石こうボード
そのほか不燃材料に準ずるもので建設大臣が指定するものを言います。
○難燃材料
燃焼速度が比較的遅く燃えにくいもので、難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板等で建設大臣が指定するものを言います。
○準難燃材料
難燃性ではあるが発煙性は有しているもので、強化ポリエステル板等で建設大臣の加熱試験に合格したものを言います。
現在、報道で注目されているニチアスの軒天板の防火性能認定試験に際しての捏造行為は不燃材料の中の石綿スレートに
属するものですが、性能的には準不燃材料同等に評価される物だったのでしょう。(2007.12月掲載)
次回は外壁材の種類と特徴を工法別に分けて説明致します。
モリス住宅総合研究所 監修
カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »
2010年7月14日
カテゴリー: 家を建てたい | コメントはまだありません »